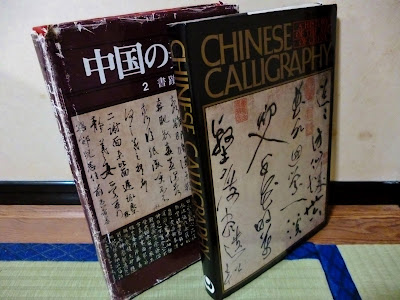「大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋」の題字がいいなあ
MIHO MUSEUMの「 大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋 」の題字がいいなあ。いい。 てらいがない。りきんでいない。そして基本は外していない。特に「徳」「天」「鞋」。 上から目線ですんません。 お寺のご住職が書いた字だろうか。 うまい人が意図的に稚拙に書いた感じもしない。そういうのもいいが、りきみがあるんだ。それはむき出しの作為だ。 メディアにちやほやされるケバケバした今風の字に疲れている目にもやさしい。 これはいい字だ。 「意識の作為や、智慧の加工が、美の敵であることを悟らねばならぬ。」 「だが稚拙は病いではない。それは新たに純一な美を添える。素朴なものはいつも愛を受ける。ある時は不器用とも云われるであろう。だが器用さにこそ多くの罪が宿る。単なる整頓は美になくてならぬ要素ではない。むしろ不規則なくば、美は停止するであろう。」 ーー柳宗悦『 工芸の道 』