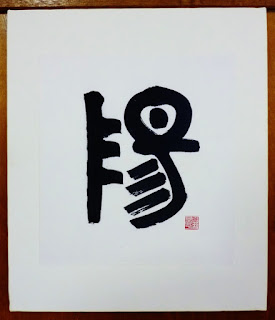日本のろうの現状を知る:大学のテキスト"Deaf in Japan"読了
I've just finished reading the textbook used in “The world of Sign Language” course at ICU. It describes the history and politics of deaf in Japan. It is a valued work among the few sources on deafness in Japan. Check out: Nakamura, Karen . 2006. Deaf in Japan . New York: Cornell University Press. 大学で「手話の世界」という授業をとっている(とこのブログに書くの は実は3回目だ)が、先ほどそのテキスト Deaf in Japan を読み終えた。恥ずかしながら、大学の教科書を全て読み通したのはこれが初めてだ。(偶然だが、私が今までに買った教科書は全て英語だった。本書はその中で一番小さい。)200余ページのペーパーバックのくせに、2610円も払ったのだ、読まなければ買い損だ(というのは建前だが、でもきっとみんなろくに読んでいない。確かめてはいないが、賭けてもいい)。 Deaf in Japan: Signing And the Politics of Identity [ペーパーバック] / Karen Nakamura (著); Cornell Univ Pr (刊) この授業の先生によると、日本のろうに関するよい著作が、本書以前は無かったそうだ(教科書にするには、という意味でだろう)。その点で本書は貴重だ。 本書は日本のろうに関する歴史と政治を扱う。もっとも 、戦後から現代が中心である。政治についてはあまり頭に入らなかったが、大事な点は押さえたつもりだ。私が特に強調したいのは、私をはじめ耳の聞こえる者は、ろうや手話についてほとんど分かっていないのが実際だということ。ろう者や手話に対する誤解は絶えない。ここでいろいろ書いてもいいのだが、書いたところで何人の人が興味を持ってくれるだろう。とりあえず、手話の定義をめぐる論争や、ろう者としてのアイデンティティの問題などなど、問題は山積みなのだ 。 著者の中村かれんは、バイリンガルで文化人類学者、イェール大学